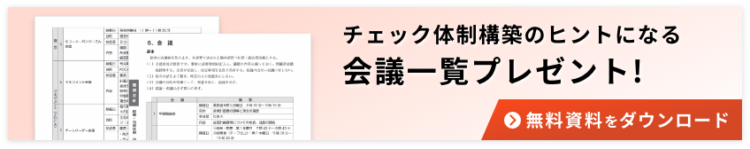【社長なら知っておきたい】平凡を非凡に変える“凡事徹底”の力
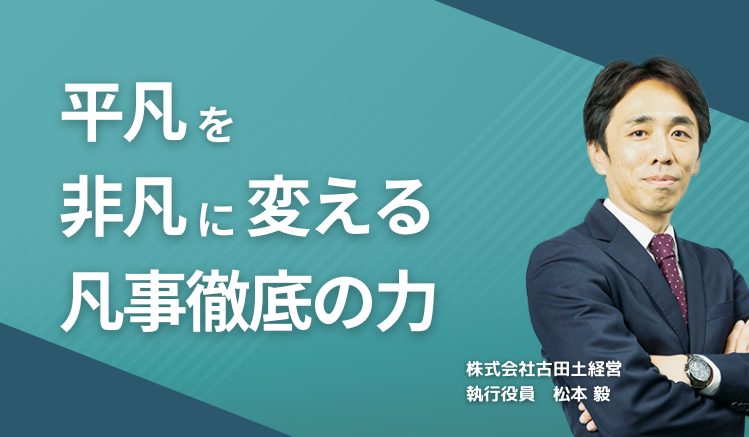
凡事徹底は、「一見平凡で誰もができるようなことを、妥協なく継続的に実践する」という意味ですが、誰でもできる凡事を、誰もができないレベル(非凡)で続けることで、他とは違う差を生み出すことができます。
弊社は、これまで4000社以上の企業とお会いしてきましたが、成果を出している会社や個人、繁盛しているお店などには、いろいろな成功要因がありますが、多くは、基本的なことを疎かにせずに、愚直に取り組んでいます。
弊社も、「挨拶」「掃除」「朝礼」を3つの文化として掲げて、毎日、実践を積み重ねてきました。当たり前の基準も高めていき、人材育成や業績を支える土台となっています。この文化や社風を見るために、数多くの会社がベンチマークとして見学に来て下さいます。
当たり前のことを当たり前のように徹底することは簡単ではありません。お会いする経営者からも、「どうしたら、全社員が基本的なことを徹底できるようになるのか?」という相談もよく受けます。
凡事徹底ができるようになると、
例えば、顧客とのコミュニケーションの質を高めるために、毎日の挨拶や迅速な対応を徹底することが信頼関係の構築につながり、顧客からの紹介やリピート率が向上する効果をもたらします。
また、5S活動や日常の整理整頓を通じて、職場環境の改善や業務効率の向上が期待できるでしょう。職場が整然としていれば従業員のモチベーションが向上し、結果的にチーム全体の生産性が高まります。
これまで取り組んできたことをベースに、凡事徹底するための考え方や具体的な事例をご紹介します。
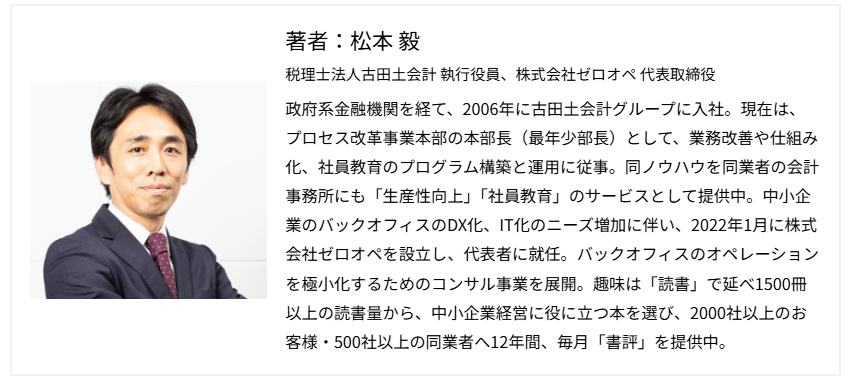
1.凡事徹底とは
凡事徹底は、平たく言うと「当たり前のことを当たり前のようにやる」ですが、成果を出している人や企業の多くは、この姿勢を大事にしています。
成果を出すためには、画期的なアイデアや特別な戦略だけでなく、基本をしっかりと守ることが求められます。1章では、凡事徹底の定義や効果を解説していきます。
1.1 凡事徹底の定義
凡事徹底とは、それぞれの言葉を辞書で調べると、
凡事・・・ありきたりなこと・あたりまえのこと
徹底・・・底までつらぬき通ること・中途半端でなく一貫していること
とありますが、まとめると、以下のような意味になります。
『一見平凡で誰もができるようなことを、妥協なく継続的に実践する』
書籍『凡事徹底 平凡を非凡に努める』の著者であるイエローハットの創業者、鍵山秀三郎氏は、
凡事徹底とは『誰にでもできる平凡なことを、誰にもできないくらい徹底して続ける』ことだとされています。
鍵山氏は掃除や整理整頓といった、日常的な業務の徹底は自己管理能力を高め、周囲との信頼関係の構築につながると説いています。
この考え方は、特別な才能や能力がなくとも、基本の徹底によって非凡な成果を生み出せるという信念にもとづくものです。
また、「凡事徹底」はビジネスだけでなく、人生全般においても活きてきます。凡事を積み重ねることで、良い習慣を増やしていくことにつながります。
1.2 凡事徹底がもたらす効果
凡事徹底を実践すると、企業や個人には以下のような効果を期待することができます。
・まわりからの信頼・自分への信頼
徹底できる力が備わると、まわりから(上司・お客様・取引先など)、基本的なことを誠実にこなす姿勢に対して、信頼を得ることができます。
また、継続できるという習慣は自分自身に対する自信につながります。
昨今、自己肯定感や自尊心が重要という話が出ますが、凡事徹底して続けることは、間違いなく自己肯定感の向上につながります。
・やり抜く力がつく(実行力)
やるべきことは分かっていても、できない・動けないといったことは誰しもあるかと思います。
一つのことを凡事徹底できる力が備わると、他のことでも徹底できる実行力を活かせることができるようになります。
「やりぬく力GRIT」という書籍がベストセラーになりましたが、大人でも子供でも「やり抜く」ことが出来ずに中途半端で終わってしまうことに悩んでいる方は非常に多いです。
・差別化できない強みとなる(成長)
どのように成長していくのかを数字でイメージすると分かりやすいかと思います。
凡事徹底して、毎日0.1%の成長をしていくと、短期間ではそこまで差が出ませんが、時間の経過と共に、大きな結果の差となっていきます。
● 1カ月:1.001の30乗 ≒ 1.0304 約1.03倍
● 6カ月:1.001の180乗 ≒ 1.1971 約1.2倍
● 1年:1.001の365乗 ≒ 1.4402 約1.4倍
● 3年:1.001の1,095乗 ≒ 2.9875 約3倍
● 10年:1.001の3650乗 ≒ 38.4046 約38倍
私自身は20代から「読書」を積み重ねてきて、15年で約1,000冊の本を読んできました。
20代に読書習慣がなく、30代になってから慌てて本を読もうと思っても、1年で1,000冊を読むことは到底できません。
また、本を読んだ知識を踏まえて、いろいろな経験をすると経験値の上がり方も変わってきます。コツコツと積み重ねていくことのパワーを実感しています。
1.3 凡事徹底の類似する言葉
「凡事徹底」という言葉は、「当たり前のことを当たり前にやる」と言い換えることができます。
たとえば、「時間を守る」は、ビジネスにおける基本ですが、このような当たり前のことを疎かにせずに徹底することが大切です。
「平凡を非凡に努める」という言葉も凡事徹底に通じます。
誰でもできるような平凡なことを、誰も真似できないくらい非凡に取り組むことで、成果を出すことができます。
ほかにも、凡事徹底と通ずる表現を紹介します。
● 微差の積み重ねが絶対差になる
● 継続は力なり
● 時間を味方につける
● 塵も積もれば山となる
● 成功のコツは二つ 「コツコツ」
● ABCDの法則
A(当たり前のことを) B(バカにせず) C(ちゃんとやる人が) D(できる人)
こういった言葉があるということは、凡事徹底が大切であることを物語っているかと思います。
自分にとって、しっくりくる言葉を定期的に見返すと、凡事徹底へのモチベーションも維持できるかと思います。
2.何を凡事徹底するべきか?
凡事徹底を実践するためには、具体的に「何を徹底するか」を明確にすることが重要です。
会社においては、社員一人ひとりが日々の基本的ことを確実に行う力が、組織全体の成長を支える土台となります。
では、どんなことを徹底するといいのか、弊社が実践してきたこと、成果を出している企業が大事にしてきたことをベースにご紹介します。
2.1 5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)
5S活動は、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の5つの要素で構成されています。
環境整備という表現もありますが、仕事をやりやすくする環境を整えて備えることができます。
弊社では、環境整備に関する方針があり、5Sのそれぞれの言葉を次のように定義しています。
「整理」・・・捨て去ること。要る物と要らない物を明確にし、要らない物は捨てる。
頭の中の古い概念、先入観、成功体験、否定の言葉を捨てる。
「整頓」・・・揃えること。人は見た目で判断する。揃えるために、位置を決める。
物を揃えることで、全社員の心を揃える。
「清掃」・・・行動すること。毎日やる。毎日やるから習慣になり、心も磨かれる。
「清潔」・・・整理、整頓、清掃を徹底することで、いつ誰が見ても、不快感を与えないようにきれいに保つ。
「躾」 ・・・4Sを習慣化すること
5Sを通じて、仕事がやりやすい環境になり生産性が上がっていくとともに、単に綺麗になるだけ以上の効果を期待することができます。
目に見える空間が整うことで、心や気持ちの整理にもつながっていきます。
最近では、朝の掃除などは、外部委託するケースも増えていますが、あえて取り組んでみるという発想も大切です。
弊社では、毎朝15分間の環境整備の時間が決まっていますので、毎日徹底することができます。
また、月に1回、環境整備点検を実施して、できているかのチェックをしています。
2.2 挨拶
挨拶は「人間関係をよくする潤滑油」といわれ、ビジネスにおける基本的なコミュニケーション手段です。
元気な挨拶が習慣化されている職場では、下記のような効果が期待できます。
・従業員同士のコミュニケーションが活発になりチームワークが向上
・お客様との信頼関係を築くための第一歩になる
・職場の雰囲気が明るくなり、空気が良くなる
・挨拶をキッカケに相手に興味を持つことになり、関係性の質につながる
挨拶の重要性について異論を唱える方は少ないのではないでしょうか?
一方で、数多くの会社を見ている中で、「挨拶を大切にしましょう」と掲げて、それが徹底できているかというと、決してそうではありません。
挨拶を浸透するために、弊社が取り組んでいることをご紹介します。
まず、挨拶をする目的は「相手を元気にするため・相手に喜んでいただくため」と定義しています。
一般的には、コミュニケーションの円滑化という定義が多いかと思いますが、抽象的で分かりづらいので、上記のようにシンプルに表しています。
元気にする挨拶とは何か?についても、このように決めています。
・相手の目を見る
・相手の名前を呼ぶ
・相手より先に挨拶する
・元気良く、笑顔で明るく、大きな声
どんな挨拶がいいのかについても定義しておかないと、人によって、これまでの人生の中で培ってきた挨拶がスタンダードなので、バラつきが出てしまいます。
目的と具体的な方法を明確にしたうえで、一番大事なのは、経営者が率先して行うことです。
トップが模範を示すことで、全員に浸透していくことにつながります。
2.3 人材育成 〜人が育つのに10年〜
「人が育つのに10年」と言われますが、これは人材育成が短期的な取り組みではなく、長期的な視野で計画的に行うべきものであると示唆しています。
人材育成をする上で2つの観点があります。技術教育と理念教育です。
技術教育であれば、知識を教えることで、ある程度、短期的に成果を期待することができます。
一方で、理念教育(考え方やベクトルを合わせる)については、時間がかかるものです。
時間を要するからこそ、日々の積み重ねが大切で、小さな取り組みの徹底が、最終的に大きな成長につながるでしょう。
具体的には、下記のような取り組みがあります。
・理念教育に関する勉強会を実施し続ける
・現場において、考え方がズレていれば、必ずフィードバックする
・定期的な面談を継続して、成長を促す
・会社として大切にしていることを経営計画書などに明文化して共有する
・個人であれば、技術や知識以外の勉強をして、実践を積み重ねる
こういったことを継続することで、「人を育てる」という文化が根付いていくことができ、育つ環境が整っていきます。
そして、育成された人材が次世代リーダーとして企業を成長させる好循環が生まれていくことも期待できます。
2.4 QSC(品質・サービス・清潔)
QSCとは、品質(Quality)、サービス(Service)、清潔(Cleanliness)の3つの基本的な要素で、特に飲食業やサービス業で重要視される概念です。
まず、品質管理の徹底は商品の一貫性を確保し、お客様に対する信頼を築くための第一歩です。
次にサービスの徹底は、飲食業などにおいては接客が中心ですが、お客様への対応を通して、お客様の評価に直結します。
さらに、清潔さの徹底は「このお店はいつも綺麗」と思ってもらえる要素となりますし、清掃が行き届いた職場は、社員が気持ちよく働ける環境にもなります。
弊社でも、飲食業、サービス業のお客様と数多くお会いしてきましたが、分かりやすいのはフランチャイズの飲食業です。
フランチャイズであれば、取り扱っている商品・メニューは一緒ですが、業績には大きく差が生まれます。
全国にあるフランチャイズで、上位5番の業績を出していたお客様は、やはりこのQSCを妥協することなく取り組んでいました。
皆さんもご存じのモスバーガーでは、
HDCを掲げ、Hospitality(心のこもったおもてなし)、Delicious(安心、安全で高品質なおいしい商品の提供)、Cleanliness(磨き上げられた清潔なお店)に取り組まれており、
基本の徹底を繰り返しながら、企業文化を作り上げていらっしゃいます。
2.5 朝礼
朝礼を実施している会社は多いと思いますが、徹底度合いには差があります。
目的が明確にあり主体的に取り組んでいる会社もあれば、惰性になってしまっているケースもあります。
朝礼は毎日のことなので、徹底するためには絶好の場となります。
弊社では、30年以上に渡って朝礼を実施しており、メディアにも取り上げられています。
朝礼は「訓練の場」と定義しており、朝礼を通じて、「挨拶」「笑顔」「話す」「聞く」といった基本動作をトレーニングしています。
野球で例えると、「キャッチボール」「素振り」「ランニング」「ノック」などを毎回、練習するようなイメージです。
毎日繰り返すことで、習慣化していき、元気な挨拶ができるようになったり、笑顔が増えていったりと、基本的な基準が上がっていきます。
こうして基本を徹底できる力が備わっていくと、他のことも実践できるようになっていきます。
また、全員で同じことを実施することで、コミュニケーションの円滑化になりますし、同じ方向性やベクトルに向かうことができるようになっていきます。
朝礼の詳細については、下記の記事にまとめていますので、ご参考下さい。
参考:朝礼とは何か?朝礼の必要性と社内を活性化させるための秘訣
凡事徹底することの事例を5つ紹介しましたが、日常的にできることでは、上記以外にも、
・時間管理、時間を守る
・PDCA(計画を立てて、振り返る)
・健康管理
・読書や勉強
などを積み重ねていくことができると、長い時間軸で成長することにつながります。
3.凡事徹底を実践する仕組み
凡事徹底を実践するためには、継続するための仕組みが必要不可欠です。努力や根性だけでは、うまくいかない可能性が大きいです。
普通のことをちゃんとやり続けるのは難しいものです。
なので、会社で何かを徹底しようとした際に、単に「やるべきこと」を指示するだけでは徹底できません。
取り組むことを具体的に明確にし、共通の認識を持つことが重要です。
凡事徹底を実践する仕組みについて、紹介します。
3.1 何を徹底するかを明文化する
凡事徹底を成功させるためには、まず「何を徹底すべきか」を明文化することが重要です。
たとえば、5S活動や挨拶の徹底といった具体的な内容を明文化し、社員に対して共有することで行動が統一されやすくなります。
明文化されたルールやガイドラインは、迷わず行動できる指針となります。
受ける側によって解釈や捉え方の違いが起きないようにするためには、why・what・howの3つの観点で整理すると伝えやすくなります。
例えば、「挨拶」を徹底しましょうと伝えても、人によって挨拶の基準が違います。下記のように整理すると、解釈のズレが少なくなります。
①what(何を) 「挨拶」
②why(なぜ) 「相手を元気にするため」
③how(どうやって) 「名前を呼ぶ、相手の目を見る、元気良く、笑顔、笑声で」
ぜひ、明文化する際には、この3つの要素を取り入れてみることをおすすめします。
3.2 強制力を働かせる
凡事徹底を継続的に実践するためには、強制力を持つ仕組みが重要です。
単に社員に「やりなさい」と指示するだけではなく、強制力のある仕組みを導入することで、自分の意志に依存することなく、取り組む環境を整えられます。
具体的な方法はシンプルです。
・やる日、時間を決めて、時間をブロックする
・自分との約束は破りやすいので、他人と約束する
・やると決めたことについては、必ずチェックする(もしくはチェックしてもらう)
といったことが効果的です。
例えば、健康のためには運動が大事だということは誰しも異論がないかと思いますが、
ジムなどに継続的に通ったり、ウォーキングやランニングを自主的に継続できるかというとハードルがあります。
だからこそ、パーソナルトレーニングのような強制力のあるサービスが世の中から一定のニーズがあります。
徹底したいことがあれば、上記のような方法で取り組むことで実施率は上がります。
3.3 フィードバック
凡事徹底を持続させるためには、フィードバックが欠かせません。
なぜなら、凡事徹底していても、遅効性ですぐに効果が出ないものもあり「これを続けて意味があるんだろうか?」という疑問が生じやすいものです。
そこで、フィードバックの仕組みがあることで、必要性を感じやすくすることがポイントです。
具体的には以下のような方法があります。
・上司など他者からの定期的なフィードバック
・行動することが評価に反映されるようにする
・定期的に定点観測して変化をチェック
・自分自身での振り返り(セルフフィードバック)
フィードバックを通じて、自身の成長や変化を実感し、継続することへのモチベーションが高まります。
4.凡事徹底の事例
凡事徹底は、様々な成功者によって実践され、重要な原則として広く認識されています。
各界の成功者たちは、一見すると平凡な日々の習慣や行動を徹底することで、卓越した成果を上げてきました。
こうした事例から凡事徹底の重要性を再確認でき、ビジネスや個人の成長に活かせます。
ここでは次に挙げる4人の成功者の事例を通じて、凡事徹底がいかに成功へとつながったのかを見ていきましょう。
4.1 イチロー選手
「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道」
イチロー選手は、凡事徹底を象徴する存在のひとりです。
高校の3年間、毎日欠かさずに、10分間の素振りを継続したエピソードは有名です。
「毎日の練習が試合の成果を作る」ことをモットーに、日々の練習や準備を徹底的に行い、安定したパフォーマンスを長年にわたって維持してきました。
また、試合前のルーティンを徹底して行い、毎回同じスイング、同じ動作の繰り返しによって試合での安定したパフォーマンスを発揮しました。
彼の成功は決して才能だけでなく、毎日のルーティンワークを決して怠らない姿勢にあったのです。
驚異的な記録達成は、ルーティンや準備の徹底なくしてありえなかったでしょう。
野球界では、野村克也氏も「凡事徹底」をチームの指導に取り入れ「当たり前のことを当たり前にやるのがプロ」と述べています。
4.2 鍵山秀三郎
「誰もがやろうとすれば出来る平凡なことを、人が驚くほど続けている人が偉大な人間」
イエローハットの創業者の鍵山秀三郎氏は「日本を美しくする会」の創始者であり、掃除を徹底することが、内面の心の状態や結果にも影響を与えると提唱しました。
「掃除は心の鏡」という言葉の通り、掃除を外部の環境を整えることだけではなく、精神を鍛える重要な行為と位置づけたのです。
鍵山氏は、社員の心を穏やかにするためには、まず職場環境をきれいにすることが大事だと思い、28歳の時に社内のトイレ掃除をひとりで始められました。
社員さんからは「掃除なんかしても無駄だ」という批判があり、手伝おうとする社員はおらず、最初の10年間は独りで続けられたとのこと。
10年を過ぎた頃から、数人が手伝うようになり、さらに20年を過ぎた頃には、多くの社員さんに浸透したとのことです。
日々の清掃活動が徹底的に行われることで、店舗の清潔さにつながり、さらには、社員のモラルやサービス精神の向上にもつながって業績にも好影響を与えました。
1993年に発足した「日本を美しくする会」は30年を迎えており、全国や世界に活動が広がっています。
鍵山氏は「10年偉大なり、20年畏るべし、30年にして歴史になる」という中国の格言を大切にされておりますが、まさに凡事徹底を体現された方です。
4.3 稲盛和夫
「平凡な人材を非凡に変えたものは、ひとつのことを飽きずに黙々と努める力、いわば今日一日を懸命に生きる力です」
稲盛和夫氏の成功事例として、日本航空(JAL)の再建は非常に有名です。
2010年に経営破綻したJALを78歳の時に引き受け、稲盛氏は凡事徹底の精神を持ち込みました。
JAL再建において「社員の意識改革」を重視し、日々の基本的な業務の徹底を促したのです。
稲盛氏は全従業員に「利益なくして安全なし」という哲学を浸透させ、個々の従業員が自らの役割を徹底する重要性を強調しました。
稲盛氏が導入した「アメーバ経営」は、従業員一人ひとりが小集団で責任を持って経営に参加する仕組みで、これも凡事徹底の一例です。
従業員が自分たちでコストを削減し、利益を追求するために、業務プロセスを細かく管理しました。
その結果、全員が経営の一部としての自覚を持ち、結果的に会社全体の業務が徹底され、再上場を果たすというV字回復を実現しました。
また、稲盛氏は「利他の心」という哲学を従業員に浸透させ、JAL再建の土台を築いたのです。
日常業務を他人のために、つまり会社や顧客のために徹底して行う意識を根づかせ、全員が自発的に改善に取り組む姿勢を育みました。
これこそが凡事徹底によって、組織の意識改革と成果に直結した好例です。
4.4 松下幸之助
「むずかしいことができても、平凡なことができないということ ではいけない。 むずかしいことより平凡なことのほうが大事である」
パナソニックの創業者として知られる、松下幸之助氏の大切にしていた考え方は凡事徹底です。
前述の5Sに始まり、道を歩く時はポケットに手を入れない、靴を脱いだら真っ直ぐ揃えるといった、日頃の身の回りのことをきちんと行う習慣を身につけさせ、人を育てる考え方です。
この習慣づけは、経営を成り立たせる上で何よりも大切な精神、正直さ、真面目さ、愚直さといった精神を育むことにもつながります。
松下幸之助氏は、伸びる会社の条件として、
①元気でさわやかな挨拶
②キッチリとした整理整頓
③掃除のゆき届いたトイレ
の3つを挙げていました。
こういった当たり前のことを手を抜かずにしっかりやるという姿勢が、人を育てることにつながり、会社としての力になることを物語っています。
5.まとめ
当たり前のことを実践できることは、大きなパワーにつながっていくことを感じ取っていただけましたでしょうか。
凡事徹底は、PCやスマートフォンでいうところのOSに該当します。
いくら良いアプリケーションがあっても、OSが古いと、アプリは機能しません。
正しいOSを導入して、更新し続ける必要があります。
記事でご紹介した通り、気合と根性だけでは、凡事徹底は難しいので、
継続するための仕組みをインストールしていただき、ぜひ、一つのことを続けていく力を備えていただければと思います。