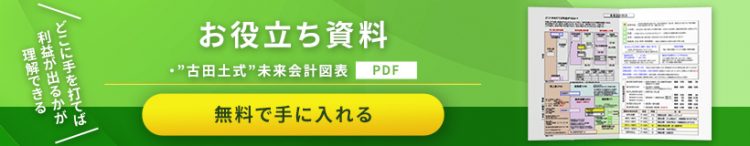儲からなくなるから値引きは駄目?
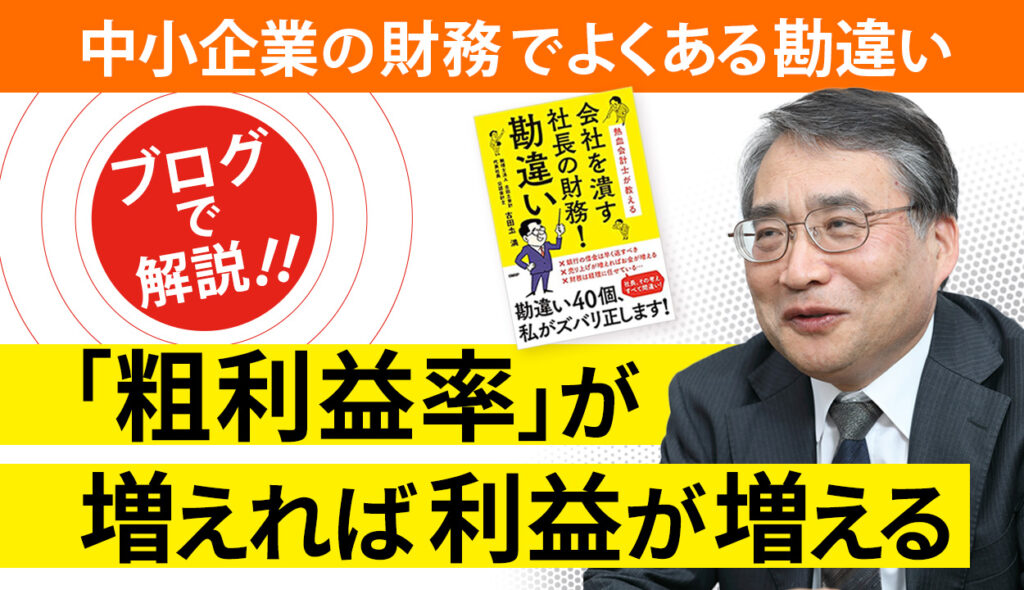
「値引きをしたらやっぱり儲からないのかな?」
「利益を出すために、どんな戦略が有効なの?」
「もっと儲かる会社にするためには、まず何をすればいい?」 などなど
このような悩みは日々つきません。
そんな企業の皆様が頭を抱えている悩みに、書籍『熱血会計士が教える 会社を潰す社長の財務!勘違い』からポイントをかいつまんで、しっかりお答えしてきます。
「儲からなくなるから値引きは駄目?」と思っている方は、ぜひご覧ください。
▽動画でも解説しています
儲かっているかは経常利益で判断する
多くの企業の経営者を見ると「絶対値引きはダメだ」という勘違いをしていることがあります。
「値引きをすると儲からないのか?」と聞かれることがありますが、実はそんなことはありません。
儲かるか儲からないかは最終的に「経常利益」を見て判断されます。
粗利益率が下がるからと言って値引きを避けるのではなく、時には値引きをしてでも販売数を上げることによって粗利益さえ増やせれば「経常利益」は伸ばすことができるのです。
つまり、会社経営で大切なことは、いかに経常利益を出すかということになり、その経常利益を出すために必要なことは「値引きをしない」ということではなく「粗利益を増やす」ということになります。
ですが、現在中小企業の課題は「粗利益」が安すぎるということです。正直、粗利益を増やすために、様々な工夫をして経費・コストの見直しから変動費を下げる、単純な生産性を高め売上高を増加させるということは、中小企業にとっては容易なことではありません。
業態によっては競合相手や市場の価格状況を分析し、時には利益度外視でも販売数を重視した戦略に舵取りをせねばなりません。値引きせずに売れなければ利益は「ゼロ」です。そうなれば経営そのものが危ぶまれてしまいますが、値引きをしたらその分の利益減で済みます。
こだわるのは粗利益率ではなく粗利益額
儲かる会社にするために大事なことは「粗利益率」ではなく、「粗利益額」にこだわるということです。
では、粗利益額を増やすためには何をすればいいのでしょうか?
それは「売上高を上げる」か「変動費を減らす(コストカット)」になります。
つまり値引きしても販売数を伸ばすことによって、しっかり売上高を確保できれば粗利益額が増えるので、その場合は粗利益率を気にせず「値引き」するべきという考えになります。
「販売数=お客様」を確保さえできていれば、しっかり粗利益額は稼げる仕組みとなっています。
指標としてもちろん「粗利益率」は大切なのですが、経営者は「粗利益額」にこだわることが重要です。
ですが、逆にその場合はお客様が減ることによる利益の減少も等しく大きいものとなりますので、商品そのものの付加価値を高め、粗利益額を増やすための努力も必要なのです。
値引きだけに限らず、業態ごとの戦略は様々あるということです。
粗利益率を1%上げるとどうなるのか?
粗利益額を増やす時に重要な指標となるのは「粗利益率」となります。
では粗利益率が1%上がるだけで、どれだけ粗利益額に影響があるのかを見ていきましょう。
例えば、売上高1000万、変動費500万、固定費400万、経常利益100万の企業があったと仮定します。
この会社の粗利益率は「売上高1000万−変動費500万=粗利益額500万」となるため粗利益率は50%となります。
仮に粗利益率が1%上がれば粗利益額が510万となるため、もともとの500万から粗利益率は2%増加したことになります。
この場合、「粗利益率1%増加=粗利益額2%増加」という仕組みになっています。
そもそも、粗利益率が低い業態は粗利益額の増加割合が高くなります。
中小企業の経営者を対象に勉強会を開催していると、自社の数字を計算され「粗利益率を1%改善するだけで、こんなにも経常利益が増えるのか」と皆さん驚かれています。
粗利益額を増やすための指標として「粗利益率を1%増加させる」という考え方が非常に重要です。
「たかが1%」ではなく「されど1%」なのです。
粗利益率の高さによって戦略は変わる
では、どうやったら粗利益率を改善させ、粗利益額を増加させることができるのでしょうか?
それは粗利益率の高い業種なのか、低い業種なのかによって取るべき戦略が異なります。
⚫︎ 粗利益率が高い業種は「量」を考える 例)「商品・サービスに付加価値をつける」
⚫︎ 粗利益率が低い業種は「価格」を考える 例)「売上増加・仕入れ価格の見直し」
当然、値引きし販売数を伸ばすのも一つの方法となります。
粗利益率を増やすには「売上高を上げる」か「変動費を減らす(コストカット)」と前述しましたが、中小企業にとっては容易なことではありません。大企業に比べ整理整頓や環境整備を行っても中小企業にとっては微々たるものですし、場合によっては値上げをお客様にお願いすることが必要なケースも出てくるでしょう。
このように値引きにしても、値上げにしても、最終的に粗利益額を高めるという目的のためには、取るべき戦略が違ってくるということを覚えておきましょう。
粗利益率が高い業種は何をすべきか?
粗利益率の高い業種であれば、「付加価値の高い商品を出し続けること」です。
他社に負けない本質的に良い商品・サービスの開発により、「お客様の数=量」をしっかり確保する必要があります。当然ですが、お客様が増えれば増えるだけ経営は安定し、逆にお客様が減っただけ利益は下がる傾向になります。粗利益率の高い業種はそれだけお客様の「数」が重要になっています。
当然、営業活動は売上を伸ばすという点においては短期的な効果はありますが、中長期的に見るとやはり根本的に商品そのものの付加価値を高めるということが重要です。これまでの商品は必ず競争相手が出てきますので、本質的に良い商品・サービスを開発することができれば安定的に販売数を伸ばすことができます。
そのために「付加価値の高い商品を出し続ける」ということが有効な戦略となるのです。
粗利益率が低い業種は何をすべきか?
逆に粗利益率の低い小売や卸業といった業種の場合は、「価格」に重きを置いた戦略が有効となります。客単価や売上原価にメスを入れ、粗利益額を確保することが重要です。
内部構造的に粗利益を圧迫するほど変動費率が高いということになるため、仕入れ一つに対しても見積もり比較を行い、価格精査をし、適正価格を見直すことが必要です。
この時に、仕入れ先を叩きすぎて安くするという考えには注意しましょう。あくまで「適正価格」をしっかり精査し、健全な経営を全うすることで企業としての「信頼」の向上にも繋がってきます。
まとめ
結論として儲からなくなるから値引きは駄目?というテーマの回答は「NO」ということになります。
<ポイントまとめ>
⚫︎ 時に「値引き」は必要な考え
⚫︎ 大切なのは「経常利益」
⚫︎ 粗利益率ではなく粗利益額にこだわる
⚫︎ 粗利益率1%の改善は、利益増に大きく関わる
⚫︎ 粗利益率の高さによって取るべき戦略は異なる
このように粗利益率の高さに応じた戦略として、何を重視するかという舵取りが重要になります。数字を勉強することによって、もっと儲けることができ、社員にも多くの給料を支払うことができます。
これらのことを経営者だけでなく社員全員へ浸透させることによって、会社一丸となって戦略的にしっかり儲かる仕組みを構築することができるでしょう。
なお、社長をはじめ社員さんの数値リテラシーを高めるためには、分かりやすい資料を使うことがポイントです。当社でお客様に実際にご提供している、『未来会計図表』をご用意しましたので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。