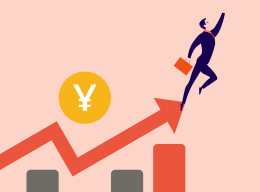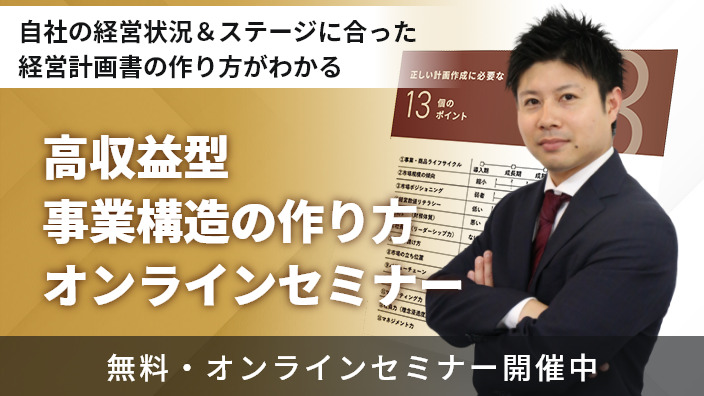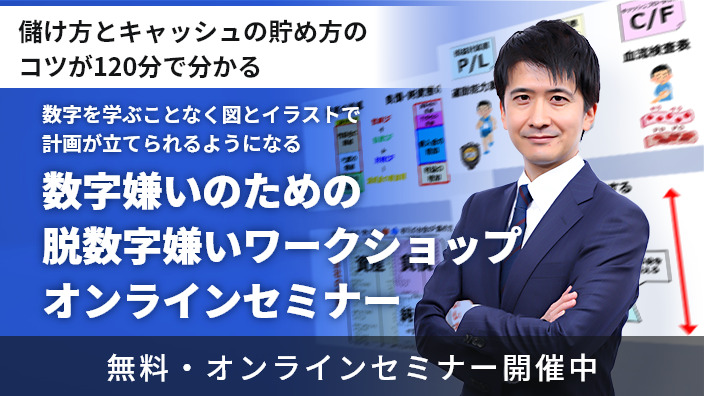『マネるだけ、埋めるだけで作れる経営計画書 作成シート(ダイジェスト版)』
無料プレゼント!
利益とは社員と家族を守るためのコスト。この考え方を全社員で共有する【社長の仕事その2】
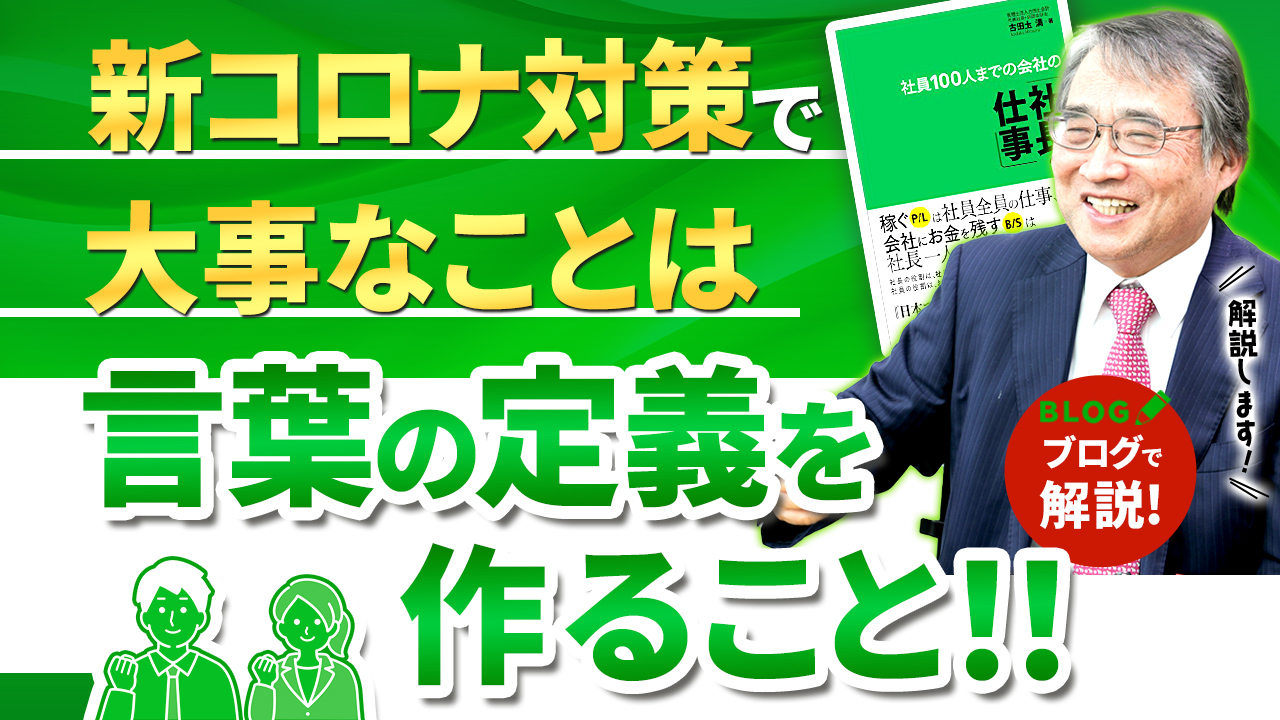
「利益とは、社員と家族を守るためのコスト」。この考え方を全社員で共有する。
社員が頑張ってくれないのは、社長が社員にきちんと働きかけていないからです。小さな会社が成長できるかどうかは、すべて社長の頑張りで決まります。
出典:古田土 満, 社員100人までの会社の「社長の仕事」, p.34
経営者の方は「利益」についてどのようにお考えでしょうか。「収益−費用」「自由に使える余ったお金」といった考えが頭に浮かんだ方は、重大な勘違いをしているかもしれません。
今回は、利益に関する正しい考え方について解説します。合理的な経営や人を大切にする経営に関心のある方は、ぜひ以下を参考にしてください。
▼動画でも解説しています。
会社経営の目的と手段
なぜ経営者は経営計画書を作るのか。
経営計画書は、社員と家族、そして会社を取りまく全ての人々を幸せにするため、会社を持続的に成長させる道具です。
出典:古田土会計「人を大切にする経営計画書」, p.1
会社経営の目的は、社員と家族を幸せにすることです。その目的を達成するための手段として、会社は持続的に成長しなければなりません。まずはこの目的と手段を十分に理解してください。
「利益」とは
利益とは、社員と家族を守るためのコストであり、「会社存続のための事業存続費」。会社存続のために必要なのは、売上でも粗利益でもなく利益です。この「利益」は、一般的な経常利益(会社が稼げる利益)ではなく、会社が稼がなければならない利益を指します。
出典:古田土会計「古田土式月次決算書」
次に「利益」をどう考えるかを解説します。
昔から簿記会計や経営を知らない人は、「利益は収益から費用を引いたもの」だとよく言います。「その差額は余ったものだから皆に分配すべきだ」と言われることもあり、現実に分配していた社長もいたようです。
しかし、利益とは「収益−費用」で求められるようなものでありません。経営者は「利益」の本質を知る必要があります。
会社が支払うさまざまなコスト
会社にはどのくらいのお金が必要なのでしょうか。
多くの中小企業は借金を抱えています。よって、まず利益の中から借入金を返済しなくてはいけません。そのため、1年間でいくら借入金を返さなければならないか、経営者が前もって知っておくべきです
会社が支払う経費には、ほかにも株主に対する配当金があります。配当金も利益で賄わなくてはいけません。また業績が良かった場合には、株主に配当を出すとともに、役員にも役員賞与※を支払います。
さらに設備投資のための内部留保も必要です。加えて、社員の将来的な賃金に備える内部留保も作っておかなくてはなりません。そのほか、財務体質を良くする目的で自己資本比率を上げるための自己資本額も求められます。
以上のような費用は、全て利益から捻出しなくてはなりません。これが、会社が稼がなくてはならない「利益」です。
※参考
2017年度に税制が変わって「事前確定届出給与」が出せるようになりました。通常、役員賞与は損金にはなりませんが、事前確定届出を出せば「利益処分の前倒し」として損金算入が可能です。
利益は会社と社員を守るために必要な金額
借入金の返済や配当金、内部留保※など、会社には利益でまかなう必要のあるコストがたくさんあります。これを理解していないと、「収益と費用の差額は余ったお金だから、全て社員に分配しよう」といった発想になってしまいます。
ほとんどの中小企業には借金があり、設備投資も必要です。そのため、利益は「余ったお金」ではありません。利益は、会社と社員を守るために会社が最低限維持しなければならない金額です。会社は利益を使って、借入金の返済や配当金、役員賞与、設備投資、人件費など、さまざまなコストを支払わなければなりません。
以上のようなことを経営者がまず理解し、そして社員にしっかり教育していくことが重要です。
※参考
内部留保を考える上で重要なのは、利益計画、とりわけ中期事業計画です。中期事業計画では、5ヵ年でどのくらいの内部留保をするかを定めます。
税引後利益の重要性
会社存続に必要なものは、粗利でも営業利益でもなく税引後当期利益
出典:古田土 満, 社員100人までの会社の「社長の仕事」, p.36
上記の通り、利益を考える上で大切なのは、税引後利益です。税引後利益だけが自己資本となり、自己資本率を高めて会社を安全にすることにつながります。
社員と家族を守るのは、P/L(損益計算書)の利益ではありません。社員と家族を守るのは「お金」です。つまり自己資本比率を高めて現預金を多く持つことが重要となります。
現預金を多く持って会社を存続させるには、税引後利益を増やすような経営が必要です。経営者は、「税引後利益がいくら必要か」という意識を明確に持たなければなりません。
繰り返しますが、利益とは、社員とその家族を守るためのコストであり、会社を存続させるために必要なお金です。この「利益」は、営業利益や経常利益でなく、税引後利益を意味します。
税引後利益が非常時に社員を守る
利益は、企業の中に内部留保という形で蓄積されていきます。内部留保は利益剰余金に分類されるお金です。このお金は、非常事態に社員を守るための原資になります。
出典:古田土 満, 社員100人までの会社の「社長の仕事」, p.37
コロナ禍では、多くの会社が日本政策金融公庫などから借金をしました。今後、その返済が本格化し、倒産する会社が続々と出てくるでしょう。
コロナ禍によって、本来なら借りられない資金がたくさん借りられました。そのため、コロナ禍のうちは赤字でも会社は持ちました。しかし、もともと赤字体質の会社は、コロナ禍が去っても利益体質にはなりません。
コロナ禍で借りたお金はすぐに使い切る。しかし返済は始まる。返済できない。以上のような流れで、倒産する赤字企業がどんどん増えていくと考えられます。
生き残る会社には現預金がある
ポストコロナで生き残る会社は、もともと内部留保が多く、自己資本比率が高かった会社、つまり現預金をたくさん持っていた会社です。
自己資本比率が高くてお金を多く持っている会社は、コロナ禍によってもっとお金を借りられました。それも無担保・無利子・無保証・返済期間10年という好条件で借りられたのです。このコロナ融資によって、自己資本比率が高かった会社の現預金はさらに厚くなりました。
内部留保の少ない会社はこれからどんどん倒産していきます。一方、内部留保の多い会社は、ライバルが少なくなる上に、ライバルが手放した店を安い値段で購入できます。従来の数分の一のコストで支店が作れます。
以上は全て財務体質の差です。内部留保の差に起因します。
会社経営はまず財務から
会社経営で大事なのは、「財務・マーケティング・人づくり」だと言われます。一番上に来るのは「財務」です。
我々中小企業はいつ潰れるかわかりません。そのため、財務を固めてから攻めることが重要です。順序を間違えてはいけません。
いくらP/Lでもうかっていても、財務の基盤である自己資本比率が低い段階で過度に業容を拡大すれば、会社は倒産します。
社員の協力を得るための数字教育
利益は社員と家族を守るために必要です。これまで解説したようなことを社員にきちんと説明すれば、「自分たちの雇用を守るために内部留保をしなくてはいけないんだ」と理解し、頑張ってくれるでしょう。
自分たちのために利益を出し、内部留保をする。そのような教育をすることが必要です。数字の教育をしないと、「利益が出ているのになぜわけないのか?社長が独り占めしてるのでは?」と考える社員も出てきてしまいます。
社員の協力なくして経営はできません。社員の十分な協力を得るため、経営者は数字や経営に関する教育を自ら行う必要があります。
まとめ:利益は社員と家族を守るためのコスト
会社経営の目的は、社員とその家族を守ること、そのために会社を存続させることです。
利益とは、会社存続のために必要な最低限のコストのことを指します。借入金の返済や配当金、役員賞与、設備投資、人件費などを捻出するために使うお金です。
またここでいう「利益」は、粗利や経常利益ではなく、税引後利益を指します。会社は非常時に備えて、税引後利益を多くして内部留保することが必要です。
以上のことを経営者が正しく理解するとともに、社員にも丁寧に説明することが大切になります。