『中小企業経営者が目指すべき利益とは』 (全社員で取り組む利益とは、銀行が見る利益とは)
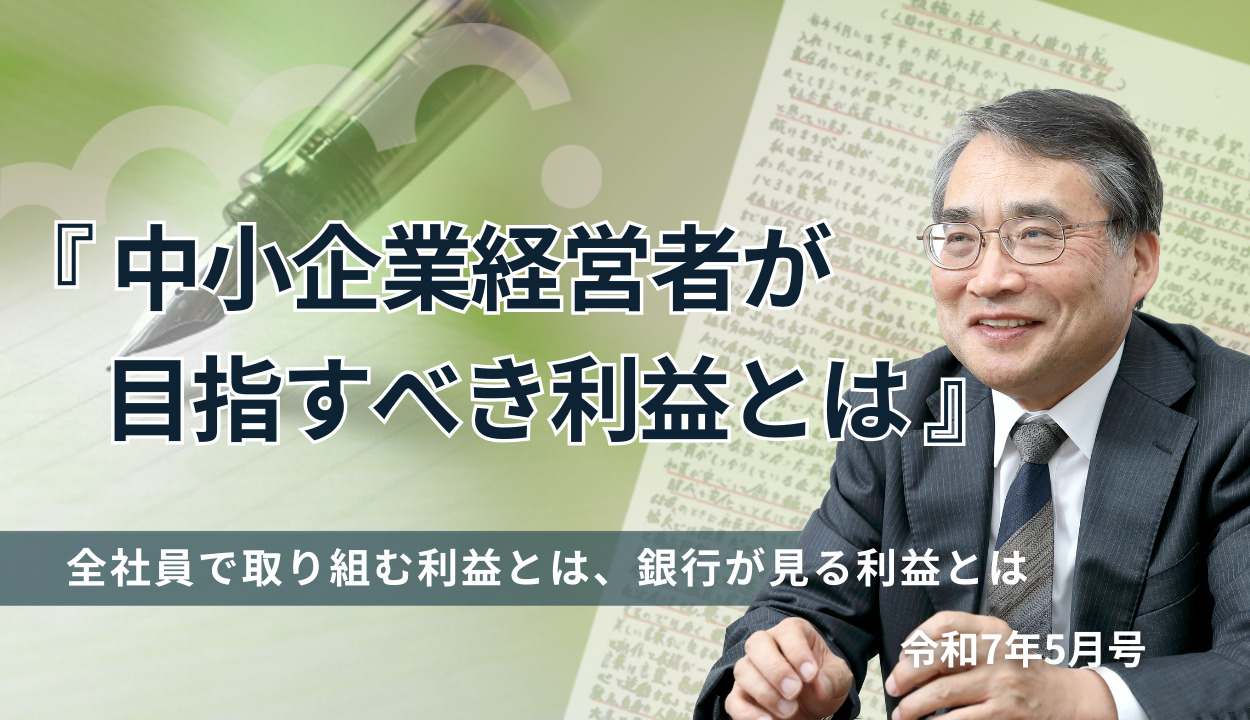
損益計算書の目的は利益である
損益計算書の目的は利益です。
「正しい利益とは短期利益計画を作成し、毎月計画と利益を対比し、差額を確認し対策を打つことです。」と何度も書かせてもらいました。
この利益は経常利益のことです。
全社員で達成すべき目標となる数字だからです。
損益計算書を見ると、さまざまな利益が表示されています。
上から順に書きますと売上総利益、営業利益、経常利益、税引前利益、税引後利益です。
経営分析で使われる利益は総資本利益率、自己資本利益率、粗利益(粗利益率)等です。
重視される利益は、目的、立場によって異なります。
中小企業は経常利益で見るべき
よく経営の本で営業利益を中心に分析しているのがありますが、営業利益は大企業の数字を分析するのには正しいのですが、中小企業では正しい経営成績を表現していません。
なぜなら、大企業や上場企業は市場から資金を調達し借金が少なく、借金があっても低い金利です。
そしてその資金を株に投資したり、M&Aの購入資金にして多額の配当金を受け取ります。その結果営業利益より経常利益のほうが高くなります。
代表的な企業がソフトバンクです。
ソフトバンクは受取配当金が益金不算入なのを利用して、税金を払っていないことで有名です。
よって大企業の業績は営業利益で見るべきなのです。
中小企業は経常利益で見るべきなのは中小企業は自己資本比率が低く、借金過多の会社が多いのが現実です。
また自社ビルや工場、営業所を所有しているか、賃借しているかで固定費としての地代家賃や支払利息が大きく変わります。
賃借している場合は製造原価や販管費に地代家賃が計上されて営業利益が計算されますが、所有していれば地代家賃が計上されないため営業利益が多く計上されます。
支払利息は営業外費用なので、経常利益で数字で見なければなりません。
そのうえ多額の借金の返済が生じますが、P/L上は表現されません。
私は持たざる経営をお客様に勧めているのは経営はB/Sが目的で、P/Lは手段だからです。P/LのためにB/Sを悪くしている会社が多いのは、財務を知らないからです。
会社はP/LではなくB/Sで潰れることを知って下さい。
重視される利益は、目的、立場によって異なる
社長の利益は税引後利益です。
税引後利益がB/Sの純資産を増加します。
自己資本比率が50%以下で節税目的のレバレッジドリースや保険、高級車等の節税商品を購入していては、いつまでたっても財務が盤石な会社になりません。
今の税率は30%位です。
経営者は給与で個人留保するより、会社で内部留保したほうがトータルの税金は少なくなります。
そして自己資本比率の高い会社に銀行は安い金利で多額の融資をしてくれ、返済条件も長くしてくれます。
銀行から見る利益は営業利益です。
社長の成績表の金融機関版で一番配点が高いのは返済能力です。
債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオ、キャシュフロー額の全てが営業利益から計算されています。
銀行にとって重要なのは貸せるかどうかではなく、返してもらえるかどうかなのです。
会社経営にとって大事なのは、粗利益(売上高-変動費)と経常利益です。
中小企業では固定費はそんなに削減できません。
大企業は平気で希望退職や解雇、人材派遣の打ち切りで人件費をカットしますが、中小企業では人件費は目的です。
増やしていかなければなりません。
人件費以外の経費の削減には限界があります。
粗利益を増やすしかありません。
粗利益を増やす道具が月次決算書の未来会計図と月次変動損益計算書です。
また利益計画は、経常利益からスタートします。
何故経常利益かというと、全社員で取り組むのは経常利益だからです。
特別損益に社員の責任はありません。
ちなみに会計事務所の見る利益は税引前利益です。
古田圡 満


