『経営を数字で語れる社員教育をする』(売上ではなく、P(客単価)×Q(客数・商品数))
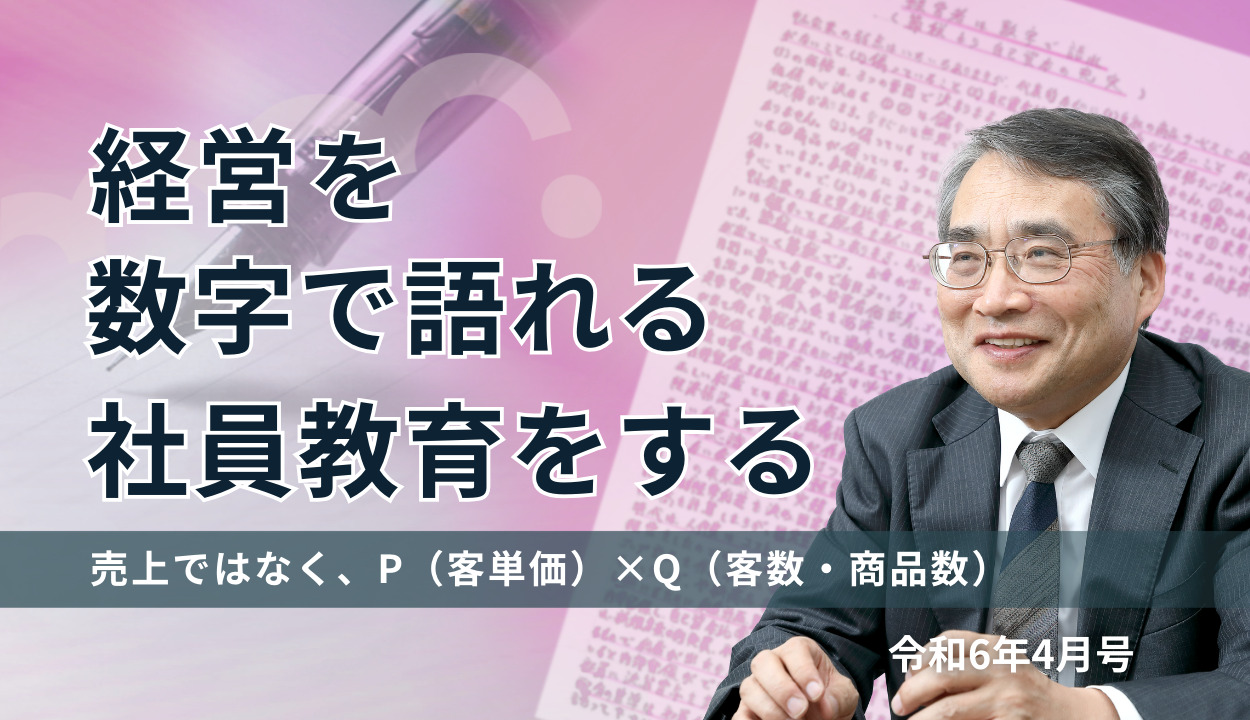
数字教育できないのは道具が悪いから
社長、幹部、社員が経営を数字で語れるようになると会社はもっと儲かると思っています。
多くの中小企業の経営者は、社員に数字教育をしていません。
私は数字教育できないのは道具が悪いからだと思っています。
何度も繰り返し言っていますが、古田土式月次決算書こそ数字教育の教科書です。
貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(C/F)、資金別貸借対照表(資金別B/S)は経営者、幹部がわかればよいのですが、未来会計図、月次推移変動損益計算書は社員が理解すべきものです。
特に未来会計図を使って社員教育をします。
具体的には、売上ではなくP(Price)単価×Q(Quantity)数量です。
変動費はV(Variable cost)変動単価。
P-V=M(Margin)付加価値単価。
PQ-VQ=MQとなり、MQ-F(Fixed cost)=G(Gain)経常利益です。
MQ÷PQがm率(限界利益率=粗利益率=付加価値率)となります。
損益計算書(P/L)の目的はGですがG=MQ-Fです。
給料を上げることを経営目標の1つにする
Fの一番大きな費用は人件費です。
中小企業の給料は、公務員や大企業に比べて低いので、これからの経営では、人件費はコストではなく、目的として給料を上げることを経営目標の1つにしなければなりません。
例えばお客様に値上げをお願いする場合に、社員に値上げをお願いするように指示するのではなく、「社員の皆さんの給料賞与をアップするためにはこれだけの値上げをする必要があるので是非とも値上げを実現しましょう」と言ったほうが社員は積極的に動いてくれます。
中小企業ではGアップのためにFダウンではなく、MQアップなのです。
MQアップのためには、PアップかQアップ、m率アップですが、Pアップにはどういう方法があるのか、Qアップ、m率アップにはどういう方法があるのか、全社員で考えるのです。
売上アップよりPアップ、Qアップと分けたほうがより具体的な方法が提案されます。
「Pアップの戦略は何がありますか」と聞くと具体的に答えられない幹部もいます。
これはしかたがありません。
今迄このように売上を分解して考えたことがなかったからです。
Pアップはまず値上げです。
今は値上げの絶好の機会です。
古田土会計では確定申告で数十年ぶりに値上げをお願いしています。
千百件あるので社員の給料アップの原資になります。
付加価値の高い商品の開発し、お客様の数を増やす
次に付加価値の高い商品の開発です。
毎年新商品を開発し続けられればPアップは実現できます。
Qアップ戦略は、まず新規取引先の開拓です。
古田土会計では今年の目標は200件です。
毎週何件増え、何件解約、そして値上げ値下げを報告してもらっています。
私達はm率100%の業種なので、客数の増加が生命線です。
ですから毎週チェックして現状を確認し、対策を打っています。
次に今のお客様により多くの商品数を買っていただくための提案をします。
例えば、社会保険は社労士法人に会計顧問、財務顧問のお客様には生保・損保の提案、事業承継対策、相続税対策、経営計画25時間合宿、給料計算、M&A等の提案です。
要は毎年少しずつお客様の数を増やし、そのお客様により多くの商品を買っていただければPQはアップし続けます。
m率のアップはP↑が一番ですが、社員教育として、m率が1%、3%、5%アップしたり、ダウンすることによりGがいくら、何%増減するのかを理解してもらうことです。
P、Q、m率の変化によりGがいくら何%増減するか社員がわかると会社はもっと儲かり、社員の数字レベルは上がります。
社内の共通言語としてP、Q、M、m率、PQ、VQ、MQ、Gという言葉があたり前のように飛び交えば全社員が創造性を発揮してGアップ、モチベーションのアップもできます。
数字教育をゲームで体験するものとしてマネージメントゲーム(MG)があります。
MGは古田土会計では1日コースを用意しています。
是非MGにより数字に強い社員を育成して下さい。
古田圡 満


