『環境整備。社員教育の目的は利益ではありません。人づくりです』 (利益中心主義の経営では人は育たない)
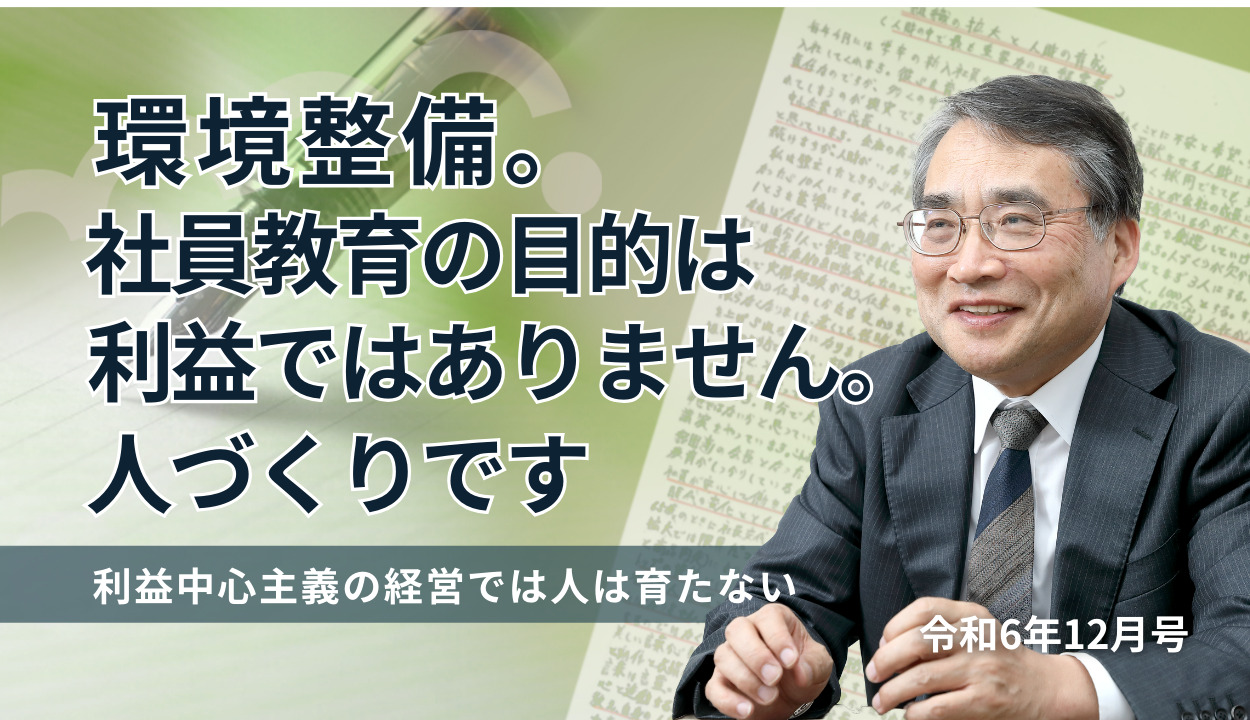
心を磨く。次に「心」より入って「形」にあらわれる。
環境整備とは、「仕事をやり易くする環境を整えて備える」と定義します。
そして「形」から入って「心」に至る。「形」ができるようになれば、あとは自然と「心」がついてくる。心を磨く。次に「心」より入って「形」にあらわれる。と経営計画書(P108)に書いてあります。
環境整備や社員教育に力を入れている会社はたくさんあります。環境整備点検として毎月1度点数をつけてチェックしている会社もあります。
皆様もご存知だと思いますが、あのビックモーターは毎月1度は厳しい環境整備点検が行なわれていました。
環境整備を徹底してやったり、社員教育に熱心な会社は一般的に儲かると言われていますが環境整備や社員教育の目的は利益を出すためでしょうか。
利益が先になると環境整備、社員教育が自己中心的になり、ビックモーターのようにお客様を騙しても会社と個人の利益を優先する会社になります。
私が思うに形ができるようになっても自然と心がついて来ないと気づきました。
心がなければ人の成長もありません。
心の教育のない形ばかりの環境整備、社員教育は自社及び個人の利益追求の手段になっているのではないでしょうか。
環境整備の目的は、人づくりであり、気づく人になること、心を磨くことである
イエローハットの創業者で「掃除道」で有名な鍵山秀三郎氏は「なぜ、トイレ掃除か」について5つの成果を語られています。
(1)謙虚な人になれる(2)気づく人になれる(3)感動の心を育む(4)感謝の心が芽生える(5)心を磨く ですが、特に(2)と(5)が大事です。
(2)の気づく人になれる とは、「世の中で成果を上げる人とそうでない人の差は、無駄があるか、ないか。無駄をなくすためには、気づく人になることが大切。」とあります。
この気づく人になれば、無駄がなくなるだけでなく、社外でも成果を上げることができます。
例えば道路にゴミが落ちていたら拾って捨てる。
有名な話では、ドジャースの大谷選手はグラウンドにゴミが落ちていたのを拾ったとして話題になって、人間力の高さが話題になりました。
サッカー国際試合でも日本のサポーターがゴミ袋を持って掃除をしている姿が放映されて世界の多くの人々を感動させました。
また、電車の中で高齢者や障がい者がいれば気づいて、自然と席を替われる人間になることが気づく人になることです。
(5)の心を磨くは「心を取り出して磨くわけにはいかないので、目の前に見えるところを磨く。特に、人の嫌がるトイレをきれいにすると、心も美しくなる。人は、いつも見ているものに心も似てくる」とあります。
環境整備の目的は、人づくりであり、気づく人になること、心を磨くことであると心の教育をして環境整備に取り組むものなのです。
会社が利益を出すための環境整備ではなく、社員の人間性を高め、お客様や世間から喜ばれ、感謝される会社、社員になるための環境整備でなければならないと思っています。
社員教育の目的は会社を取り巻くすべての人々を幸せにするため
社員教育も同じです。
社員教育の目的を「利益です」と定義すると社員教育は手段になります。
教育のしかたも利益中心、業績中心になります。
社員に高いノルマを与え成果の出ない社員は怒られ、人間性まで否定されます。
人によってはうつ病になり、家族まで不幸にします。
社員教育の目的は利益ではありません。
目的は人づくりであり、会社を取り巻くすべての人々を幸せにするためであり、良い社風を創るためです。
人は人によってほめられたり、感謝されることによってモチベーションが上がり、成長していきます。
多くの経営者に伝えたいことは、社員の幸せは、経営者の考え方によって決まります。
世のため、人のため、社会に貢献する人財を育てることが使命です。共によい社会を創っていきましょう。
社員教育、環境整備により、社員の人間性が高まり結果として儲かることがあるべき姿です。
古田圡 満


